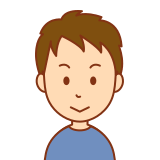
この記事では”唐辛子”の基本的な栽培法を解説しています。
唐辛子とは?
トウガラシは、その種類の豊富さと栄養価の高さで知られています。
この植物は、ピーマンやパプリカを含む広い範囲にわたり、形状や色、辛さの度合いにおいても多様性を持っています。
辛いものから全く辛くないものまで、その範囲は広く、辛味を持つものと甘味を持つものの両方が存在します。
ここで注目したいのは、辛味成分であるカプサイシンには抗酸化作用があり、ビタミンCやカロテンなどの栄養素も豊富に含まれている点です。
トウガラシの用途は非常に幅広く、薬味としての使用だけでなく、野菜としての価値も高いです。
特に、辛みが特徴の「鷹の爪」や「八ツ房」などは、料理にアクセントを加える際に適しています。
筆者は毎年タクワンを漬けていますが、漬ける際に鷹の爪を糠(ヌカ)に混ぜて漬け込みます。
漬きあがるとピリッと辛く美味しく漬き上がりますよ。

また、甘味種の「シシトウ」や辛くない「伏見」は、生食や加熱調理に向いており、その柔軟性は料理の幅を広げてくれます。
さらに、葉トウガラシも食用になり、辛いものから辛くないものまで、あらゆる品種が利用可能です。

最近では、メキシコ料理に適した強い辛みを持つ品種や、生食や炒め物に適した辛みが少ない淡緑色の大果型品種など、新しい品種の開発も進んでいます。
これらの進化により、トウガラシはさらに多様な料理に活用されるようになり、その可能性は無限大です。
トウガラシの世界は、辛さだけでなく、栄養、用途、品種の多様性においても非常に魅力的なものです。
トウガラシ栽培、畑の準備~定植
畑の準備を始める際、まず最初に行うべきは土壌の改良です。
2週間前には、土壌のpH値(※)を調整するために苦土石灰(※)を均等に散布し、土に混ぜ込むといいんですね。
肥料のpH値は、植物の生育環境を大きく左右する重要な要素です。pHは0から14のスケールで示され、7が中性、数値が小さいほど酸性、大きいほどアルカリ性を示します。適切なpH値を維持することで、土壌中の栄養素の吸収効率が向上し、植物の健全な成長を促進するとされています。※ 苦土石灰
苦土石灰は土壌の酸性度を調整するために使われる石灰の一種です。農業や園芸でよく利用されます。
その後、1週間前には土壌の肥沃度を高めるために完熟堆肥と元肥を追加し、再び土としっかりと混ぜ合わせます。
畑を耕した後、畝を作る作業に移ります。
畝の幅は70cmとし、高さは15~20cm程度が理想的です。
このサイズにすることで、植物が根を張りやすく、また水はけもよくなります。
畝を作ったら、地温を上げ雑草の発生を抑えるために黒色ポリマルチを使用します。
これは、水分の蒸発を防ぎつつ、害虫の寄り付きにくい環境を作るのに役立ちます。
定植の際には、植物の根鉢を崩さないように注意深く植え付けます。
根鉢を保持したまま、浅めに植えることで、植物は安定し、成長の基盤をしっかりと築くことができます。
植え付けた後は、植物が倒れないように支柱を立て、必要に応じて誘引することが大切です。
これにより、植物は風などの外部からの影響を受けにくくなり、健康的に成長していきます。
このように、畑の準備から定植にかけては、土壌の改良から畝作り、植え付けに至るまで、細かな注意を払う必要があります。
適切な準備を行うことで、植物は最適な環境で成長し、豊かな収穫をもたらしてくれるでしょう。
定植後~収穫の栽培管理
定植後の管理は、植物の成長と収穫量に大きく影響します。
具体的には、整枝や追肥が重要な役割を果たします。
初めに、整枝について説明します。
これは、植物の健全な成長を促し、病害虫のリスクを減らすために行います。

トウガラシなどの植物では、主枝の第一花が開花した後、その下に出現する力強い側枝を2~3本選んで残し、それらと主枝を合わせて3~4本の枝を育てるのが一般的です。
このとき、トウガラシの枝は比較的壊れやすいため、選んだ枝には支柱を設置してしっかりと支えることが必要です。
次に、追肥についてです。
植物が健康的に成長するためには、適切な栄養が不可欠です。
定植から2~3週間後に初めて追肥を行い、その後は2~3週間ごとに追肥を繰り返しましょう。
この定期的な追肥により、植物は安定して成長し、最終的には豊富な収穫をもたらしてくれます。
植物の生育状況を観察しながら、これらの栽培管理を適切に行うことで、健康的な植物の育成と豊かな収穫が期待できます。
日本の主なトウガラシの種類
日本の主なトウガラシ
■鷹の爪(タカノツメ)
日本で最も有名で、辛味が強く多くの料理に使われる。
鷹の爪(とうがらし)は、特にカプサイシンという成分が含まれており、これが主な温熱効果を発揮します。
カプサイシンは、体を内部から温める作用があり、特に寒い季節には冷え性の改善に寄与します。
具体的には、カプサイシンが体内で血流を促進し、体温を上昇させる効果があるとされています。
鷹の爪を摂取することで発汗が促され、代謝が改善されるため、ダイエット支援にもなるとか!
これは、辛さによる発汗作用によって体温が上昇することで脂肪燃焼が加速するためなんですね!
筆者は狩猟が趣味でした。猟場で手足が凍えるような寒いとき、ハンターシューズの中に真っ赤な”鷹の爪”を入れて猟をした記憶があります。
■万願寺とうがらし
京都の伝統野菜で、甘味があり、炒め物や煮物に最適。
■伏見とうがらし
軽い辛さと甘味が特徴で、主に焼き物や煮物に使う。
■観賞用トウガラシ
食用のみならず!

まとめ
1.畑の準備
・苦土石灰でpH調整
・完熟堆肥と元肥で土壌改良
・70cm幅、15-20cm高さの畝作り
・黒色ポリマルチの使用
2.定植
・根鉢を崩さないよう浅めに植付け
・支柱立てと誘引
3.栽培管理
・主枝と2-3本の側枝を残して整枝
・定植2-3週間後から2-3週間おきに追肥
これらの基本的な管理を適切に行うことで、健康的な生育と豊かな収穫が期待できます。


コメント